 |
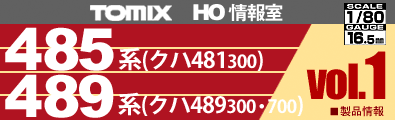 |
485系の非貫通形のリニューアル発売と共に 『489系(クハ489-300・700)』を新発売! 今回は『489系』の見どころを中心にご紹介いたします。 |
2013.08.22up |
 |
| 485系は、1968(昭和43)年にデビューした交直流特急形電車です。ボンネットスタイルで登場しましたが、モデルチェンジが行われ、1972(昭和47)年には貫通形の200番代、さらに1974(昭和49)年には非貫通形となった300番代が登場しました。この非貫通形は、1500番代、1000番代へと受け継がれ、485系の新しい顔となりました。全盛期から数は減ったものの、現在でも活躍する姿を見ることができます。 489系は、485系をベースに信越本線の横川〜軽井沢間でEF63形と協調運転が可能な車両として、1971(昭和46)年に登場した交直流特急形電車です。同系もボンネットスタイルで登場しましたが、ベースとなった485系に合わせてモデルチェンジが行われ、1974(昭和49)年に登場した300・700番代は、485系300番代と同様に非貫通形となりました。この300・700番代は、489系の中では一番新しいグループだったものの、碓氷峠廃止後も近年まで活躍していた初期型のボンネットスタイルに比べ、一足早く姿を消しています。 今回発売する『485系(クハ481-300)』は、2000年に発売した従来品をベースにリニューアルしており、新たに『489系(クハ489-300・700)』が加わります。ラインナップは、両形式の4両基本セット、増結用に485系と489系で兼用のモハユニットの2両セットをモーター付とモーターなしで2種、さらに485系では車掌室付のモハ484形600番代を含むモーターなしの2両セットも用意しています。また、単品では485系と489系兼用のサハ481(489)形、サロ481(489)形、サシ481(489)形の3種を揃えています。 なお、本製品の発売により、従来品の『485系』は生産中止となります。 |
 |
 |
| 同じように見える先頭車ですが、485系300番代(写真左)はコンプレッサーを運転台下に設置しているため、助手席側の運転台側面にルーバーがありました。 489系300番代(写真右)はコンプレッサーを床下に搭載しているため、ルーバーがありません。 製品でもボディの新規製作によって、485系と489系で異なる側面部を作り分けています。 |
|
 |
 |
| コンプレッサーを床下に搭載したクハ489形のうち、碓氷峠を越える際に横川方となる700番代(写真上)は2機搭載しており、1機搭載の300番代(写真下)と床下機器の構成が異なっています。これは、碓氷峠通過時に空気バネのエアーを抜いて走行することから、圧縮空気の復帰に要する時間の短縮を図るため、出力を増強したもので、貫通形の600番代から続く特徴です。 製品では、700番代特有の床下も新規で製作し、ボディのみならず番代で異なる床下機器の違いまで的確に再現しています。 発売中の『EF63形』と合わせて、かつ ての協調運転を再現してみてはいかがでしょうか。 |
| 485・489系の最終形として、全国を駆け巡った非貫通形。 往年の活躍を模型の世界で再現してはいかがでしょうか? 次回の情報室もお楽しみに! |
Copyright. 2013. TOMYTEC